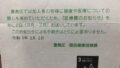当事務所の特徴
- 代表税理士が全ての業務に対応します
- オンライン打合せ可能。全国対応可
- 多くお金が残る節税策をご提案
- 顧問は申告のほか決算納税予測など対応
- 事業を始めたばかりでお困りの方向け
- フリーランス・個人事業主、中小企業専門
- クラウド会計に強く、経理の効率化を推進
- スポットでのご相談も対応
- 話しやすい若手税理士をお探しの方向け
- 詳しくはこちら→当事務所の特徴
サービスメニュー
税務顧問

税務申告から月次決算、節税提案まで継続してサポートします
【単発】法人決算・申告

法人決算・税務申告のみ対応してほしいという方向けです
個人確定申告

個人事業主、フリーランス、副業の方の確定申告を承ります
税コラム一覧
新着記事
人気記事
個人の確定申告
消費税・インボイス
小さい会社の税金
節税あれこれ
経理のコツ
税務調査・融資
代表メッセージ

当事務所のHPを御覧いただきありがとうございます。
代表税理士の金澤宏紀です。
当事務所は、代表税理士の金澤宏紀が責任を持ってすべての業務を行っております。
業務内容は、個人事業主や中小企業のスモールビジネスを行っている方を専門にサービスを提供しており、オンラインで全国のお客様からのご依頼も承っております。
スモールビジネスについては「小さい=不安定」という思いを抱かれている方も多いと思います。ですが決してそうではありません。
スモールビジネスの「速く小回りが利く」という利点を活かせば、どんな時代でも強く生き抜く経営体質を作ることができます。
その経営体質とは、つまり「手元のお金が増える経営体質」です。
それを実現させるためには、スピードに加えて、「堅実さ」を育てていくことが重要になります。
「堅実さ」は、適切な経理の積み重ねで徐々に備わっていくものです。
地道ですが、経理を疎かにしては経営の頑丈な土台はできません。
スピーディーに、そして正確に経営判断を行うためには、ご自身のビジネスの数字の理解は不可欠です。
はじめは何もわからなくても心配はいりません。
「理解したい」「事業をより良くしたい」という実直な想いをお持ちであれば大丈夫です。
わからない点は一つ一つ丁寧にサポートし、解決いたします。
「小さくても強く生き抜く経営」を実現し、お金の不安から解放され、
仕事もプライベートも、人生そのものが楽しく豊かになるよう、お役に立てれば幸いです。